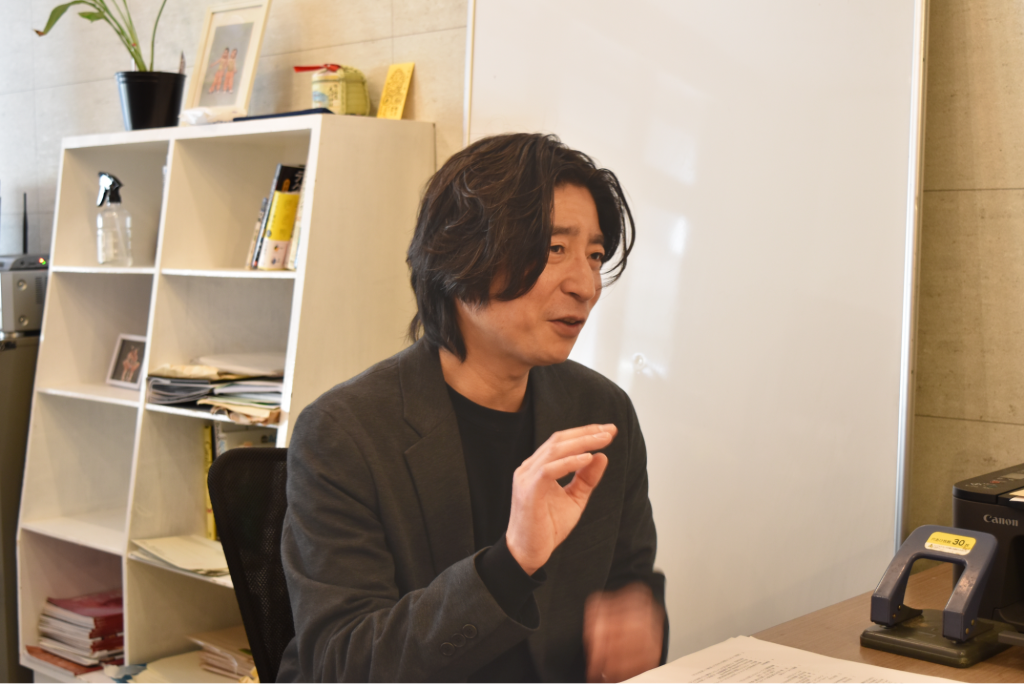予想外の展開を楽しみ事業の可能性を広げる
眠っていた端材に新たな価値を見出した竹之内製材所の挑戦

宮崎県で国産木材の加工と販売を手がけてきた竹之内製材所。バブル崩壊後の和室需要減少など、業界の変化に柔軟に対応しながら、端材を活用した「枕屏風」の開発など、新たな木材活用の道を切り拓いてきました。現在はBig Advanceを活用したビジネスマッチングで販路拡大に取り組み、インバウンド市場という思わぬ可能性も見出しています。創業100周年に向けて無垢材の魅力を広める挑戦を続ける同社の取り組みを、三代目の竹之内代表にお聞きしました。
株式会社竹之内製材所 代表取締役 竹之内 昭裕 様
83年の歴史を紡ぐ老舗製材所の事業転換
—竹之内様のご経歴について教えていただけますか?
私は地元の高校を卒業後、福岡の大学で経営学を学びました。大学進学当時から、ゆくゆくはこの会社を継ぎたいという気持ちがありましたが、父の勧めもあり、まず外の世界で経験を積むべきだと考えました。
昭和61年に大手住宅メーカーに入社し、福岡支店で5年ほど住宅営業として働きました。当時はまだバブル前夜でしたが、徐々に経済が上向き、バブル期には住宅需要も非常に高くなりました。お客様との信頼関係を築くために、自分をさらけ出し、本音で付き合うことの大切さを学びました。
平成3年頃、バブルが崩壊した時期に父から『そろそろ帰ってきたらどうか』という話があり、勤めていた住宅会社を退職し、父の経営する竹之内製材所に後継者として入社しました。それから30年以上が経ちます。
—御社の歴史と事業内容について教えてください。
当社は戦後の高度経済成長期、国産材、特に杉の需要が高かった時代に成長しました。当時の住宅は和室が中心で、私たちが製造していた『節のない高級な化粧柱(割柱)』が重宝されていました。
しかしバブル崩壊後、生活様式の変化によって和室の需要が減少し、当社の主力製品だった割柱の需要も減少していきました。こうした変化に対応し、現在は主に公共施設工事、特に学校や役所などの内装の木質化(内装や外装など見える部分を木材で仕上げること)に使用される杉板の製材に重点をシフトしております。

—木製の「枕屏風」というユニークな製品を開発されたそうですね。
製材業では、建築材料として利用される木材は2mまでが主流です。それより短い材、特に1m以下の材は利用できずに廃棄処分や粉砕してつくる畜産用のおがくずの原料になることが多いのですが、節のない綺麗な材が廃棄されるのはもったいないと考えました。そこでSDGsの観点からも、この端材を有効活用できないかと考えて思いついたのが、布団で寝る際に枕元に置く風除けとして伝統的に使われてきた『枕屏風』です。ヒノキの白っぽい木目と杉の赤みがかった木目をハイブリッドに組み合わせた屏風は、地元高原町のふるさと納税の返礼品としても採用されています。布団だけでなく、ベッドでも使えるように背の高いタイプも開発しました。
—枕屏風はどのような方々に支持されているのですか?
ヒノキとスギの香りを枕元に漂わせながらゆっくり休んでいただくという『快眠サポート』の面もアピールしており、特に医師などの健康や睡眠の質を重視する方々から好評をいただいています。
温泉旅館でお客様に枕屏風を試用していただき、アンケートを実施したところ、見栄えの良さや癒し効果について高評価を得ています。特に『ゆっくり休めた』という声が多く、満足度は高い一方で『少し重たい』といった改善点も見つかりました。

ビジネスマッチングで実現する新たな木材ビジネスへの期待
—Big Advance導入の背景を教えてください。
これまでは製品市場を通じた卸売りが中心で、過去には特に営業活動をしなくても木材が売れていた時代がありました。しかし、輸入木材の増加や生活様式、建築様式の変化により国産材の需要が減少、営業を強化していく必要がありましたが、住宅営業の経験しかない私にとって、異業種へのアプローチは難しい課題でした。そんな中で、地元の金融機関支店長からBig Advanceをご紹介いただいたのが導入のきっかけです。
Big Advanceを選んだ決め手は、ホームページの作成機能やビジネスマッチング機能、そして手頃な月額費用でした。小規模企業にとっては費用対効果を考えることが重要ですが、リーズナブルな料金設定が導入の後押しとなりました。また枕屏風やパーテーションの販売量を増やしたいと思っていたので、Big Advanceが新たな販路開拓の糸口になればいいなと考えました。

—ホームページ作成で工夫されたことはありますか?
私はアナログ人間なので、最初は自信がなかったのですが、本格的なホームページづくりに挑戦してみました。最初のポイントは「まず始めてみる」ことです。最初から完璧にすることを求めずに、他社のホームページを参考にしながら少しずつ掲載文面や写真を準備し、何度も校正を繰り返しながら自作のホームページを完成させました。
活用のコツとしては、写真の撮り方にもこだわることです。製品の特徴がよく伝わるアングルで撮影し、木目の美しさや質感が伝わるように心がけました。また、内容の更新や新着掲載も定期的に行うことで、訪問者に鮮度の高い情報を提供することができます。
—ビジネスマッチングの活用方法と成果はいかがですか?
2023年10月から本格運用を始めました。ビジネスマッチングでは積極的に商談を申し込むとともに、売りたい自社製品の魅力(ニーズ)を詳細に掲載することで問い合わせを待つという双方向のアプローチを取りました。これまでに当社から12件の商談を申し込み、全国の会員企業からも11件の商談依頼をいただいています。
成約には至っていませんが、予想外の収穫もありました。掲載ニーズから当社を見つけ、他のものも作れないかといったお問い合わせをもらうこともあり、意外な商談につながることもあります。こうした「思わぬ展開」を楽しむ姿勢も大切だと思います。
また、海外向けのECサイトを運営されている会社からお声がけいただいたことから、インバウンド需要の可能性を感じました。いくつかのサイト運営会社とは、これから面談を予定しています。やはり円安が続いている今、海外の方々向けの販売チャネルも開拓したいと考えています。
—インバウンド需要に対してはどのような展開を考えていますか?
古民家住宅をインバウンド向けに改装した宿泊施設があるんですが、ヨーロッパからのお客様が多く訪れています。皆さん日本の和文化に非常に興味を持たれているので、そういった方々に向けて当社の枕屏風を提案しています。
また、DIY向けのパーテーションキットなど、新たな製品開発も進めています。コロナの時期には、飛沫防止のパーテーションを兼ねたオフィス用間仕切りのDIYキットをふるさと納税で出していました。最近は、図書館などで勉強する学生向けの折りたたみ式の集中ブースを試作している段階です。

—Big Advanceを活用する上でのポイントやこれから活用する企業へのアドバイスはありますか?
一番のポイントは「予想外の展開を楽しむこと」だと思います。最初から完璧な結果を求めるのではなく、使いながら可能性を広げていくことが大切です。異業種とのマッチングは、当初の目的とは違う形で展開することが多いです。当社の場合は製品販売だけでなく、インバウンド需要という思わぬ市場発見につながりました。
また、ビジネスマッチングでは、できるだけ詳細な情報と魅力的な写真を掲載することが効果的です。閲覧する側は文字情報だけでなく、視覚的な情報で判断することも多いですから。
もう一つ大切なのは、地域の金融機関との関係を活用することです。地域の金融機関から展示会の案内など、さまざまな情報提供があります。Big Advanceを紹介してくれた金融機関の担当者とのコミュニケーションを大切にすることで、より多くの可能性が広がります。
『かきがらを断捨離し』創業100周年へ向かう挑戦
—今後の展望について教えてください。特に心がけていることはありますか?
最近、司馬遼太郎の『坂の上の雲』を読み返しました。その中で海軍参謀の秋山真之が述べた言葉に共感しました。
『軍艦というものは遠洋航海に出て帰ってくると、船底にかきがらがいっぱいくっついて船あしがうんとおちる。人間もおなじで経験は必要じゃが、経験によってふえる智恵とおなじ分量だけのかきがらが頭につく。知恵だけ採ってかきがらを捨てるということは人間にとって大切なことじゃが、老人になればなるほどこれができぬ。』(司馬遼太郎著,1969年,坂の上の雲(二)より、原文まま)
私も60歳を過ぎ、経験を積み重ねることで知識や情報も増えていきましたが、それが固定概念として凝り固まると、新しい発想や前向きな取り組みの妨げになることがあると感じています。『かきがら』を断捨離し、常に新しい情報をBig Advanceというアンテナから受信して、これまでの人生航海で得た知識や智恵と一緒に咀嚼しながら今後の事業展開のヒントを得たいと考えています。
また、木材の中でも特に無垢材(加工を施していない天然木材)の良さをもっと多くの人に知っていただきたいです。初代神武天皇ご生誕の地とされる地元、宮崎県高原町にある狭野神社の樹齢400年の杉のような貴重な木材は、一つ一つの年輪が緻密で複雑な模様を持ち、世界に一つだけの木目を生み出します。そうした天然素材の製品開発は、SDGsの観点からも意義があると考えています。
神代の頃から人々の暮らしの中で、五感に浸透してきた表面意匠に使用される木材(無垢材)の品揃えを拡充しながら、ニッチな役物木材の百貨店を目指して創業100周年に向かって進んでいきたいと思っています。
<会社情報>
| 株式会社竹之内製材所 | |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県西諸県郡高原町大字広原4949番地 |
| 設立 | 1952年3月 |
| URL | |
| ※情報と肩書は取材当時のもの ※一部画像は竹之内製材所様提供 | |