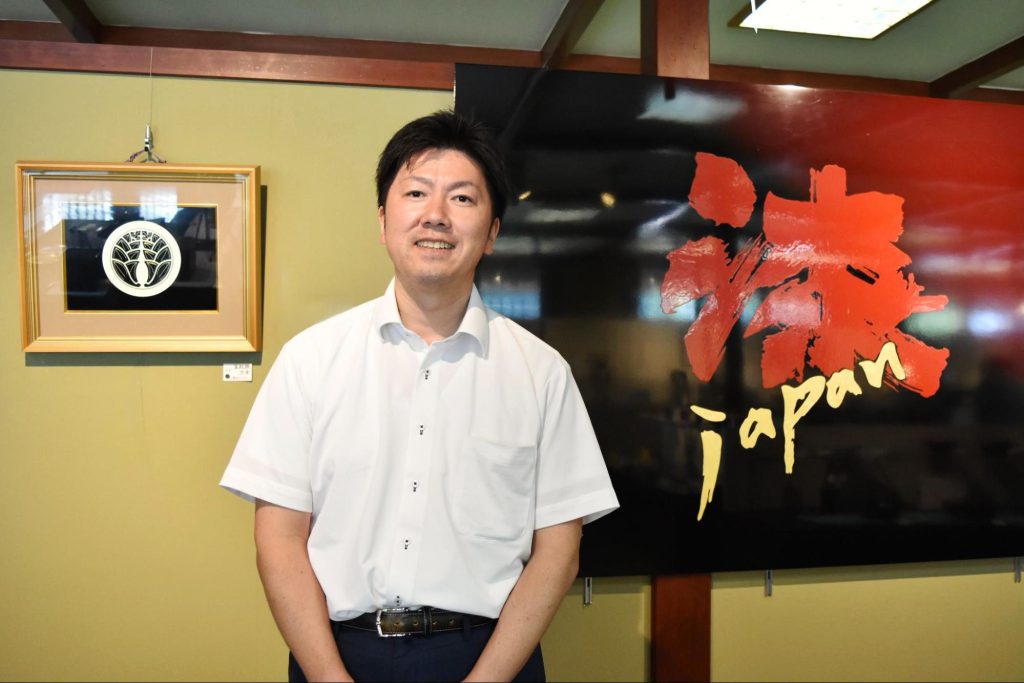バイヤー視点の地方企業発掘法!
アップ・スウェルが明かす商談の秘訣

バイヤーが明かすビジネスマッチング成功の秘訣──。ITとコマースの二本柱で事業展開するアップ・スウェル株式会社では、産直ギフト事業でBig Advanceを積極活用。商品選定から価格設定、写真の見せ方まで、バイヤー目線でのマッチング術と、地方の隠れた優良企業との出会いについて、事業開発部の小宮山氏に詳しくお聞きしました。
アップ・スウェル株式会社 事業開発部 小宮山 様
手書き伝票200枚から始まったコマース事業
─御社の事業概要について教えてください。
当社は2009年に設立し、IT事業とコマース事業の両方を展開しています。アキネーターなどの海外アプリを国内向けにローカライズしてリリースすることから始まりました。
コマース事業のきっかけは、取引先からの「相撲のカレンダーを海外向けに売りたい」という依頼でした。最初は手作業で、渋谷の郵便局に手書きの伝票を持ち込んで海外発送していました。多い時は100、200個の荷物を手書き伝票で持ち込むという状況で、相当大変でしたが、この経験が社内で「ものを売る事業もやっていきたい」という機運につながりました。
現在は小売事業と卸事業を展開しており、卸事業ではギフト商材を中心に、食品ギフトの取り扱いに力を入れています。また、従業員数は1桁台で、ITエンジニアが半分を占めるという特徴的な構成になっています。
コロナ禍で見えた食品ギフト市場の可能性
─食品ギフトに注力されるようになった経緯を教えてください。
雑貨を中心に扱っていたのですが、卸先のお客様との商談を重ねていく中で、「やっぱりギフトは食品の方が人気がある」ということが分かってきましたし、ギフト事業を伸ばすためには雑貨だけでは限界があると感じていました。それが昨年(2024年)の夏頃ですね。
とはいえ、食品を扱うには設備の問題がありました。当社は神奈川県小田原市に常温倉庫を持っていますが、食品管理に適した環境ではありません。例えばチョコレートなら28度以下をキープしなければならないといった温度管理も必要です。生産者の方々が厳しい衛生基準で作られている商品を、適切でない環境で保管するわけにはいきません。
冷凍食品なら可能ではないかなど、様々な模索はしたのですが、産地直送をされている企業さんのユニークな商品をECサイトで紹介するという方法にたどり着きました。
─コロナ禍の影響で、市場環境にも変化があったのではないでしょうか。
実は、ちょうど食品ギフトをやりたいと思った時期に、外的な環境も整ったんです。コロナ禍を経て、消費者側ではオンラインで商品を買うことに抵抗を感じる人が減りました。これまで百貨店やカタログギフトが主流だったギフト市場でも、オンラインで探すことが一般的になってきています。最近は、オンラインでのギフト取引の流通額が増えてきていると言われています。
一方、サプライヤー側では、ふるさと納税やネット通販にチャレンジする動きが増えた結果、冷凍設備を導入される企業も増えました。設備は整っているけれど売り方が分からない、という状況が多かったんです。
私たちが提案したい商品は、大きな百貨店にあるような有名ブランドの人気商品ではなく、日本の産地の名前がしっかり入った特産品や、現地に行かないと出会えない商品なんです。こうした様々な要因がうまく絡み合って、産直ギフト事業を本格的に始められる環境が整いました。

Big Advanceで解決した全国サプライヤー発掘の課題
─Big Advanceを利用されるようになったきっかけは?
食品ギフトを本格的に始めようと考えた時に、どうやってサプライヤーさんと出会っていけばいいかという課題がありました。大型の展示会にも足を運びましたが、B to Bの大手企業向けの商談をされているサプライヤーさんが多く、私たちが求めているような小回りの利く柔軟な取引には向いていませんでした。なかなか私たちが欲しい商品とマッチングできなかったんです。
そこで Big Advanceの商談会に参加しました。
宮城県で猫のモチーフのお菓子を製造している企業さん(NEKO竈株式会社)は、Big Advanceの商談会で出会った中で最も長いお付き合いです。猫の肉球の形をしたお菓子で、モチモチした食感のユニークな商品で意外に需要があるんです。インターネットだからこそ目に留まる商品なのかもしれません。
商談会は、最初はどう進めていけばいいか手探りでしたが、回数を重ねるごとにサプライヤーさんが何に困ってこの商談会に参加されているのかが見えてきました。
都市部の展示会には出展していない隠れた優良企業を発見
──参加されている企業にはどのような特徴がありますか?
参加企業は大きく2つのタイプに分かれます。一つは、有名なデパートや百貨店に商品を並べたいという意識をお持ちですが、生産量の問題やオペレーションの組み立てに課題がある企業です。
もう一つは、小売店や飲食店で、メインの仕事の隙間時間を使って商品の販売をしたいという企業ですね。毎日販売するのではなく、少量作って売っていきたいという方々です。
いずれの企業も、すでにメインの売り場はあるが、新しくインターネット販売にチャレンジしたい、販売チャネルをもう一つ広げたいという時に商談会に参加されることが多いんです。オンライン販売の設備は整っているけれど、売り方が分からなかったり売り場を探している点は共通しています。
また、具体的に「こうしてやってみたい」と考えている企業が多いことも特徴です。見積もりもしっかり出してくださる企業が多く、真剣にインターネット販売などの販路拡大に取り組もうとしている方々です。
─オンライン商談ならではのメリットはありますか?
都市部の展示会に出展できない地方の企業と多く出会えることです。地方の企業の場合、都市部の展示会に参加するには移動費、滞在費、出展費用、さらにはブース設営費用など、相当な費用がかかります。実際、展示会に出展できる企業は限られてきますよね。
先日は種子島の企業と商談しました。種子島まではなかなか行けませんが、オンライン商談なら北海道でも九州でも気軽にお話しできます。
─Big Advanceの魅力はなんですか?
最大の特徴は、金融機関の方がフロントにいることで、取引先として信頼できることです。企業取引の条件として、重要な安心材料になっています。少なくとも、金融機関と何らかの取引がある会社さんが集まってくれているということは、安心感があります。
▼アップ・スウェル様も参加決定 2026年2月の商談会エントリー受付中!
バイヤーが明かす商談成功の必須条件
─サプライヤーと商談する際に、どのような点を確認していますか?
まず、商品の見積もりをしっかりご提示いただけるかどうかです。卸値だけでなく、小売価格も含めた値付けをある程度考えられているかが重要です。「お好きな価格をつけてください」という企業もいらっしゃいますが、適正価格のイメージは持たれておいた方が良いと思います。そうでないと、原価コントロールや製造計画がうまくできていないように見えてしまいます。
食品であれば、賞味期限を最低2週間担保していただくこと、受注から3~5営業日以内に出荷していただくことなど、具体的な取引条件も提示させていただいています。また、商品情報がしっかり整備されていることも必須です。
PL保険(生産物賠償責任保険)への加入も基本的な条件です。保険に入っていないと、何かあったときに対応しきれませんから。
─インターネット販売で成功するためのコツはありますか?
まず商品を選びに来た人の目に入る1枚目の写真で購入が決まってしまうので、見せ方は非常に重要です。食品なら食べているシーンが想像できたほうが良いです。中身が見える写真は必須ですし、温かいものは湯気が立っていないと美味しそうに見えません。
以前、木製のインテリア商品を作られている企業とお話ししましたが、商品単体の写真はあっても、お部屋に飾られたイメージ写真がありませんでした。サイズ感や使用シーンが想像できないと、インテリア商品は購入に繋がりません。
また、出荷時の梱包で、あともう一工夫していただければと思うこともあります。例えば、出荷箱の縦・横・高さの合計を60cm以内に収めれば送料が数百円安くなるのに、という場合です。
─バイヤーとして、商品選定で重視していることはありますか?
当社の取引先の中から、どの売り場に適した商品なのかを見極めることです。当社は複数のオンラインギフト販売企業と取引していますが、それぞれの売り場で売れる商品は異なります。分かりやすい例が価格帯で、3000円以下の気軽なギフトが売れる売り場と、5000円以上の改まったギフトが売れる売り場では、お客様の層が全然違いますし、使われるギフトの場面も異なります。商品の特性を理解して適切な販路を選ぶことが成功の鍵になります。
企業の皆さんは素晴らしい商品を作られていますが、見せ方や売り方は別のノウハウが必要です。私たちインターネットビジネスをしている側の方が見えることもあるので、そういったアドバイスも商談の中でお伝えしています。
自動化システムで実現した完全産直モデル
─システム化にも力を入れられているそうですね。
当社の強みの一つは、ITエンジニアがいるため自社でシステム開発ができることです。現在、産直の仕組みをほぼ完全に自動化しています。発注書作成から出荷依頼、入金処理まで、8割方は自動化が完了しており、2025年10月には全工程が自動化される予定です。
また、B to Cの場合、送料を計算することがサプライヤーさんにとっては手間なんです。そこでヤマト運輸さんとご相談して送り状発行システムを活用して解決しました。サプライヤーさんは送り状を出力するだけで、送料は当社に請求が来るシステムです。サプライヤーさんは送り先による送料を心配せずに商品発送することができ、当社は発送状況をほぼリアルタイムで把握できるという利点もあります。
ITの力で双方の手間を削減し、サプライヤーさんが製造という本来の業務に専念できる環境を作っています。サプライヤーさんには「商品を作って、梱包して、送り状を貼って出荷する」といった基本的な作業だけに専念していただき、当社は販売に集中する。そうすれば新商品の開発にも取り組んでいただけますし、新たな良い商品を当社が販売できるようになります。このような好循環を作っていきたいですね。
─この仕組みを他の企業にも提供する予定はありますか?
実は、私たちが構築した産直システムを、他の企業にも提供できないか検討しています。手作業でB to C販売をされている企業の事務作業を軽減し、製造・商品に集中していただけるよう、ITの力で改善したいと思っています。

当社は小さな会社ですが、ITエンジニアが半分を占めるという特徴を活かして、実際に自分たちが使って運用しているシステムだからこそ提供できる価値があると考えています。
また、大手ECモールでも産直商品の販売を始めたいと考えています。サプライヤーさんと一緒に売り場を広げて、全国の「地域の宝物」をより多くのお客様にお届けしていきたいですね。
<会社情報>
| アップ・スウェル株式会社 | |
|---|---|
| 所在地 | 所在地 東京都渋谷区道玄坂1-15-3 |
| 設立 | 設立 2009年7月 |
| URL | |
| ※情報と肩書は取材当時のもの | |